リバイブの想い
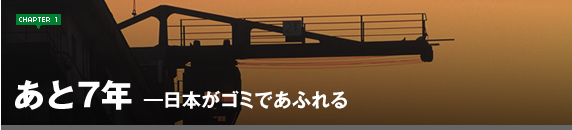
「産廃処理」という仕事
私たちは毎日建築現場などから運ばれてくる大量の産業廃棄物を分別しています。産業廃棄物には様々なものが混ざっていますが、それらを出来る限り資源として分別し、社会に還元することが私たちの仕事です。
リバイブでは、搬入される産業廃棄物を約15種類に細かく分別し、コンクリートやアスファルトなどを機械で粉砕することで再資源化したり再生施設へ搬入したりしています。
全国には私たちリバイブのような中間処理施設が約2万ヶ所、最終処分施設が約2500ヶ所、そしてこれに携わる産廃処理業者の数に至っては、ざっと二五万業者も存在しています。
あと七年――日本がゴミで溢れる
こんなにも多くの施設や業者が存在しているにも関わらず、資源として分別できずに埋め立てられる産業廃棄物は年々増加の一途を辿っています。そこには、現在の日本の廃棄物処理の構造に大きな問題があるからです。
その大きな問題の一つは、「複合廃棄物」。
私たちリバイブでは搬入された廃棄物をすべて人の手を使って分別しますが、それは人の手でなければ正確に資源として分別できないからです。それほど現在の廃棄物は複雑な原材料が組み合わされており分別が難しいものになっています。
例えば石膏ボード。安価な上、扱いやすいということで広く利用されている建築資材です。原材料は紙と石膏であり、うまく分離できれば、紙は再生紙に、石膏は路板材などに再利用できます。しかし、分離のための専用機械が必要であることや、コストも高く、また湿度が高いとうまく分離できないなど、リサイクルをする上ではこの上なく手間がかかる廃棄物なのです。このような複雑な構造の廃棄物は資源として分別できなければ、最終処分場で埋め立てられることになります。もしこのまま永遠に埋め立てることができれば何も問題はありません。しかし、日本の最終処分場で埋め立てることが出来る残余年数は実はあと7年ほどしかないのです。
問題の先送りは不可能
最終処分場を新たに建設するには周辺地域の理解を得なければなりません。しかし、感染の危険がある医療廃棄物や周辺の土壌を汚染する有害物質の不法投棄など、心無い産廃業者の行いが、地域住民の理解をますます遠ざけているのが現状です。実際に最終処分場が建設されても、地下に汚染物質が染み出さないよう遮水シートを敷いたり、処分場が廃棄物で満杯になった後も、処分場から出る水の管理をその後何年も徹底するなど、運営コストは莫大なものになります。
私たちリバイブの現場にも毎日大量の廃棄物が搬入され、出来る限りの分別を行っていますが、それでも分別できず埋立処分をせざるを得ない多くの廃棄物が出てしまいます。このままこの問題を放置しておけば、数年後には確実に日本はゴミで溢れ、自然環境が破壊されるだけでなく、再資源化が出来ないということは、急速な資源の枯渇を意味するのです。
資源枯渇――もはや手に負えない問題
最も深刻なのはプラスチックなどの原料である石油。現在の残油量はちょうど富士山をひっくり返した形の下から2合目ほどしかなく、新しい油田の発見量よりも消費量が上回っています。このままでは約20年後には確実に枯渇すると見られ、石油に依存しきっている現代農業の事情を考えれば、世界中で30億人くらいが餓死をしても不思議ではないと警告する学者もいます。
なぜ廃棄物が減らないのか。それは、あらゆる原材料があまりにも安く輸入できるため、一度使った材料を高いコストをかけて回収・再生するよりも、廃棄して新しい原材料で作ってしまうほうがずっと安上がりだからです。
もはや私たち産廃業者が運び込まれてくる産業廃棄物を分別するだけでは限界がきています。すでに手には負えない深刻な問題となっているのです。
